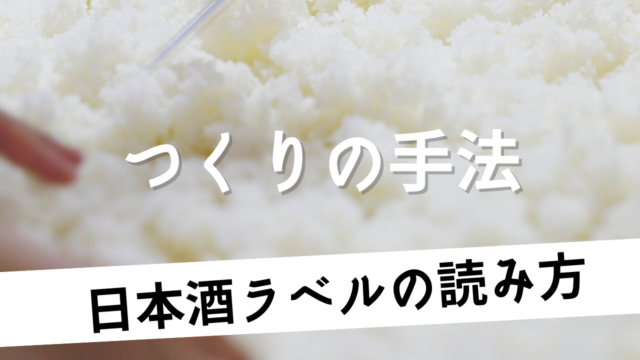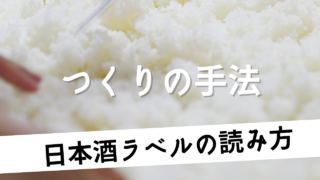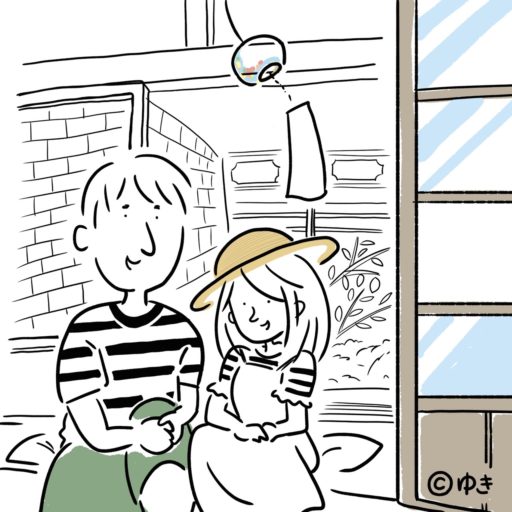私たち夫婦が毎月定期購入している日本酒定期便の体験記事を書きました!ご参考にどうぞ!
▶▶日本酒定期便「saketaku(サケタク)」が楽しい!【毎月2本届く】
こんにちは。日本酒大好き旦那です。
本日は使用酵母について見ていきたいと思います。
※ちなみにトップ画は「もやしもん」に出てくる「酵母」のキャラクターです。

酵母の役割とは
酵母は糖からアルコールを生成する
さて、酵母というのはどのような役割を果たしているのでしょうか。
かなりざっくりとした説明をすると、酵母のおかげでアルコールができている、といえるでしょう。

参考:漫画もやしもん
そもそも日本酒がアルコール発酵するのに必要なのは、お米、麹、酵母です。
酵母は糖を食べることで、アルコールと二酸化炭素を排出します。
ですが、ただの米に酵母を入れたところで、アルコール発酵はしません。
なぜかというと、お米はデンプンで出来ているからです。
デンプン=糖ではありません。
麹がデンプンを「糖」に変える
ここで登場するのが「麹」というものです。
麹のおかげで、デンプンが糖に変わります。

参考:漫画もやしもん
これでめでたく糖ができたので、酵母が糖をアルコールと二酸化炭素にします。
酵母について
酵母の特徴
それではまず酵母の特徴を見ていきましょう。
酵母はレモンのような形状をした約5~10μ(ミクロン)の大きさで、自然界では果実や樹液、花の蜜などに多く生息している。ひと口に「酵母」といっても多種多様な種類があり用途もさまざまだが、酒造りにおいては清酒酵母、ビール酵母、ワイン酵母、ウイスキー酵母などが使われる。とりわけ「清酒酵母」は低温でもよく発酵し、アルコールの生成能力と耐性がきわめて高く、代謝産物として造り出された香味が優れていることが特徴である。
日本酒の吟醸香と酵母の関係
フルーティーな香りがする日本酒を飲んだことがありますか? アルコール臭さだけではなく、最近では女性でも飲みやすいような日本酒というのも注目されつつあります。
その「フルーティーな香り」づけをしているのが「酵母」なんです。
酵母が糖を食べた後に分解されて発生するアルコールと二酸化炭素の中に含まれる、「カプロン酸エチル」と「酢酸イソアミル」という香気成分がこのようなフルーティーな香りを生成しているのです。詳しく見てみましょう。
あのなんとも芳しい吟醸香を形成する成分は、大別すると2つの香気成分、酢酸イソアミルとカプロン酸エチルに分けられる。
前者は「バナナあるいはメロン系の果実香」、後者は「リンゴ、洋ナシ、パイナップル系の果実香」がするといわれている。口に含むと、前者がサラリとしているのに対し、後者はやや重たい印象を受けるのも特徴といえる。
そのほか、β-フェニルエチルアルコールが「バラの香り」、テルペンアルコールが「ライチ、白桃、マスカット系の果実香」の素になるというから文系出身者にはややこしい。
これらはいずれも専門的には「官能評価」といい、味や香りを「甘い、辛い」「キレがいい」「コクがある」「フルーティ」といった言葉で表現し、最終的に「おいしさ」を測るのだという。
酵母の種類
そんな酵母ですが、大きく分けて「協会酵母」と「独自酵母」の2つがあります。
協会酵母
かつては酒造に住み着いている酵母をつかい日本酒造りをしていたそうですが、どうもこうも品質が酒蔵によってバラバラだったようです。
そこで、1906年に日本醸造協会が設立されるとともに、品評会で良い成績を残した酒造の酵母を採取し、純粋培養するようになったと。
これを協会酵母といいます。以下、一部抜粋です。
主な協会酵母
協会6号 香りは低く、まろやかな味わいになる。
協会7号 香りが高く、燗に向く酒になる。人気の酵母。
協会9号 果実系のさわやかな香りを出すようになる。人気の酵母。
協会10号 酸が少なく、淡麗な味わいになる。
協会11号 アミノ酸が少なく、アルコール度数の高い酒になる。
協会14号 酸が少なく、香りの穏やかな酒になる。
酵母の種類を知る:日本酒造りと協会酵母
ちなみに小ネタとして、1番古い協会酵母ってどれか分かりますか?
まあ数字を見れば分かるんですが、協会6号っていうのが1番古いんです。
5号までの酵母は戦前に頒布中止となってしまいました。
協会6号酵母は昭和10年(1935)に秋田「新政」の蔵の醪から誕生します。
発酵力が強く、香りはおだやかで、まろやか。淡麗な酒質に最適な酵母で、全国の酒蔵からの評判も良いんです。
ただ、協会酵母はいわゆる綺麗な酵母です。(個人的主観)
品評会で金賞を取るような酵母です。
それはそれでハズレはなく、間違いなく美味しい。
でもそれだけでは物足りなさを感じてしまう人もいるのではないでしょうか。
独自酵母
独自酵母とは、それぞれに個性がある酵母です。ただ、この酵母の開発には莫大な時間と労力、お金がかかります。でもその分人の思いまで溶け込んでいます。
主な県の独自開発酵母
花酵母(秋田) 香り成分が協会酵母より倍以上で、香はかなり高いらしい。酸度が低く、膨らみのある味で後味も軽い。
山形酵母 協会9号と比べて香りは高く、味の切れがよい。花酵母より香りは低い。
うつくしま夢酵母 香りのバランスに優れ、協会9号より強い。酸度が低いため、味はきれいに感じる。
アルプス酵母 他県酵母、協会9号と比べて、含み香りが特徴。燗にも向くらしい。
静岡酵母 協会9号より華やかで軽い香り。糖度のバランスに優れ、辛口でもきれいで丸みを感じる。
熊本酵母 協会9号の原型。
酵母について、実際の開発ストーリーを知るとさらに好きになると思います。福島の「うつくしま夢酵母」のお話がとても素敵なので、ぜひ見てみてくださいね。
まとめ
酵母は味や香りにも大きく影響しています。酵母の種類が書いていないラベルも多いのですが、ぜひ書いてあるときには意識してみると面白いかもしれません。